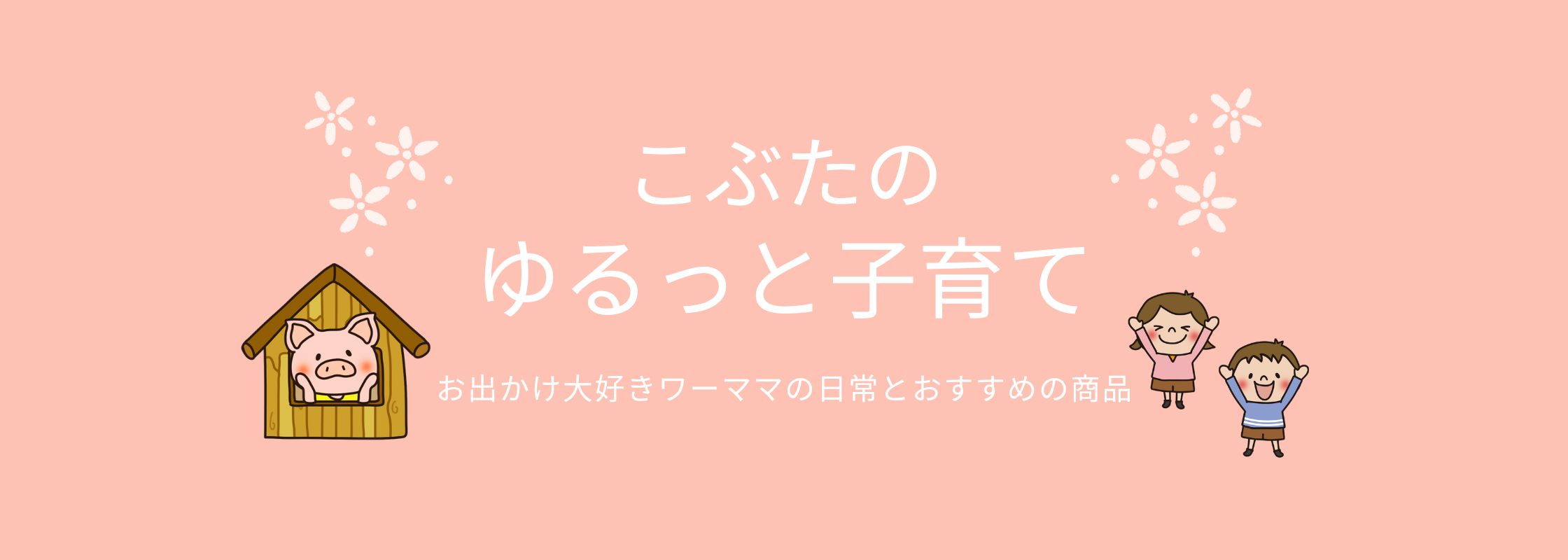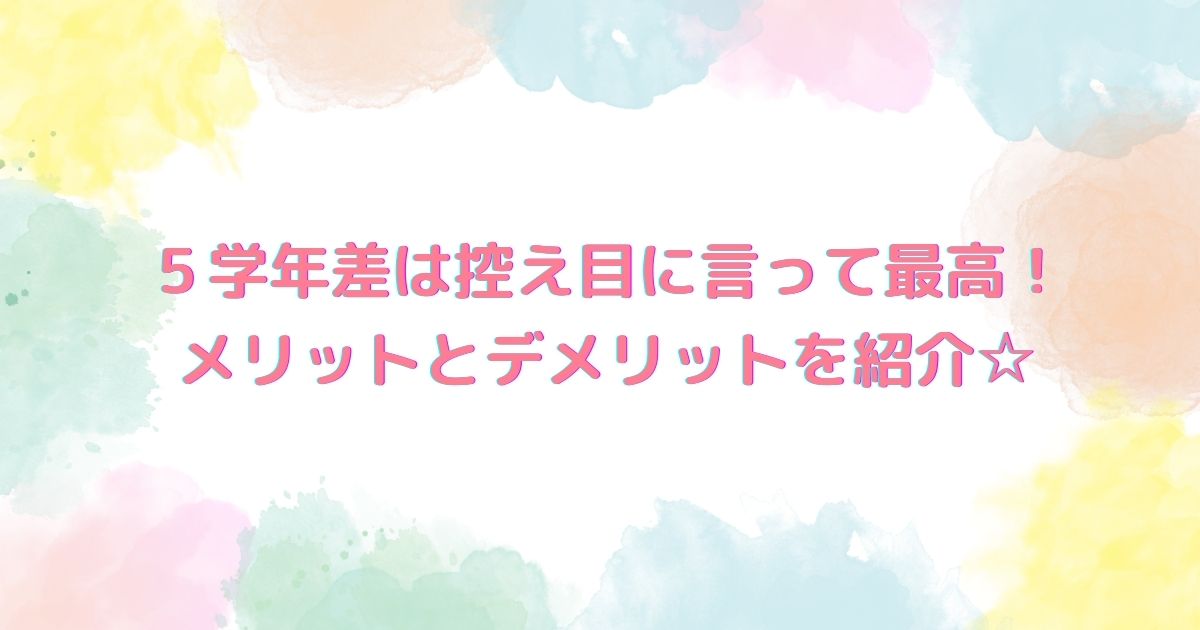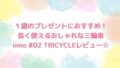我が子たちは5学年差の姉弟。
正直に言うと、我が家は「計画的5学年差」ではなく「5学年差になってしまった」タイプですが、実際産まれてみると我が家には5学年差が合っていたなと思いました。
今回は実体験をもとに、5学年差育児のメリットとデメリットを詳しく紹介していきます!
5学年差のメリット
5学年差のメリットを9つご紹介します。
妊娠期がラク
私つわりが重いタイプで、下の子妊娠中は入院を経験し、退院しても自宅で寝たきりの日々でした。
そのころ上の子は年中さん。
自分のことはある程度自分でできていたので、上の子のお世話をつきっきりでしなくてよかったのはとても助かりました。
産休に入ると、上の子が保育園の間に自分時間がとれたのもよかったです。
産後がラク
上の子は日中は保育園に通っているので、その時間は下の子と二人きり。
あかちゃんと一緒に横になり、産後の身体を休めることができました。
お世話がラク
5年ぶりの子育てとはいえ一度は通ってきた道なので、下の子のお世話は上の子のときに比べて楽に感じました。
また下の子が赤ちゃん期のとき、上の子はお世話がしたい年中~年長さん。
離乳食を食べさせてくれたり遊び相手になってくれたりと、上の子が下の子のお世話をたくさん手伝ってくれました。
なによりお世話している姿がかわいい!!!!
下の子が成長した今でも、私の料理中には下の子に読み聞かせをしてくれたりと、たくさんお世話してくれています。
お出かけがラク
上の子の荷物は基本的にいらない、必要な場合でも上の子自身が持つことができるので、お出かけの荷物が少なくてすみます。
何よりも助かったのは「ほんのちょっと見ててほしいとき」に上の子が見ててくれること!
外出先でトイレのあとに手を洗うほんのちょっとの間、上の子がベビーカーに乗っている下の子を見ててくれるだけで、ものすごく助かりました。
おさがりがたくさん
年の差が近いと「上の子と下の子のサイズが一緒になっちゃった」という話を耳にすることがありますが、5学年差ともなればサイズがかぶることはまずありません。
上の子のおさがりはもちろん、おともだちもおさがりをくれたりするので、我が家のように性別が違っても、おさがりがたくさんあります。
体操服や給食着等の学用品もおさがりできるので経済的です。
おもちゃもたくさん
下の子が産まれた時点で、上の子のおもちゃがたくさん。
下の子は常に対象年齢以上のおもちゃで遊んでいるので、ブロックやパズルやその他もろもろの習得が早かったように思います。
入園入学年がかぶらない
進学するときって、精神的にも金銭的にも気合いが必要ですよね…。
5学年差だと進学のタイミングがまったくかぶることがありません!
大学生活もかぶらない
仮に2人とも4年制大学に進学するとしても、上の子が卒業してから下の子が入学となります。
大学費用や下宿代等々のことを考えたら、大学生活は大きな出費。
それがかぶらないのはとても助かります。
下の子は上の子の友だちにめちゃくちゃかわいがってもらえる
5学年差ともなると、上の子の友だちの妹弟の中でも小さいほうに入ることが多いです。
そのため、姉の友だちからめちゃくちゃかわいがってもらえています。
5学年差のデメリット
5学年差のデメリットを5つご紹介します。
1歳入園だときょうだい加点がつかない
下の子が1歳入園の場合、上の子が保育園を卒園したその春に下の子入園となります。
そのためきょうだい加点なしでの保活となります。
保育園の兄弟割も使えませんでした。
子育てがいつまでもおわらない
上の子小学校6年生のとき下の子1年生なので、小学校だけでも11年関わることになります。
ただ、上の子が6年生のときにお世話する1年生が下の子なのかと思うと、キュンとします。
下の子が上の子の邪魔をする
上の子がレゴやアクアビーズなどにはまった時期に下の子が赤ちゃん期だったため、上の子が細かいおもちゃで遊ぶ時間や場所が制限されることがありました。
また小学校入学当初はリビング学習をしていた上の子ですが、下の子があまりに邪魔をするので急遽上の子の部屋をつくりました。
結果的に姉は自分の部屋を手に入れることができたのでよかったみたいです。
お出かけ先に困る
上の子と下の子では興味関心が違うので、お出かけ先に困ることがあります。
子ども支援センターは未就学児が対象なので、小学生にあがった上の子を連れていけないことも。
家族でお出かけの時は上の子チーム(娘と夫)と下の子チーム(息子と私)に分かれて行動することもあります。
下の子の生活が乱れる
かかりつけの歯医者さんに言われるのが「いろんなものの食べ始めが早いのは下の子の特権」!
おかし類や油ものなど、食べ始めるのはやはり早かったです。
上の子の学校時間や習いごとに、下の子が振り回されることもしばしば…
ただ就寝時間は、下の子を寝かしつけている間に上の子はひとりで過ごすことも可能なので、いまのところ大きな崩れはなくこれています。
我が家が5学年差になった理由
ずばり「2人目不妊」です。
私は子どもが大好きなので、「子どもは3人」「2学年差くらいで」なんて思っていました。
上の子は独自のタイミング法で妊活をして、半年ほどで妊娠。
でもつわりがしんどくて辛くて2カ月の休職を余儀なくされました。
そして誕生した娘はめちゃくちゃかわいかったけど、かわいいだけじゃないんですよね。
眠いし疲れてるしで娘が1歳くらいまでは、夫とそんな雰囲気にもなりませんでした。
やっと重い腰を上げ始めたころには2学年差は無理になっていて、自己タイミング法で3学年差は玉砕、病院に通ってタイミング法+内服で4学年差もやっぱりだめ。
やっとやっとやぁっっと妊娠した結果5学年差でした。
今では我が家にはこのタイミングが合ってたんだなーと思っています。